- 当選テーマ
2023年度 当選テーマ
第1回となる今回は、51件の応募がありました。応募いただいた皆さまに感謝申し上げます。3名の審査員による審査から6件のテーマを決定いたしました。
- 当選テーマ名(応募順の記載)・応募者氏名(敬称略)、所属
- 光ピンセット法によって捕捉した微粒子を用いたプラズマ電界の高精度測定と電界揺らぎの評価
- 佐藤 斗真
(九州大学大学院システム情報科学府 白谷研究室) - 国土保全のためのCyber-Physical インフラメンテナンス
-
片山 広樹、小林 健
(東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻 地域/情報研究室) - 大気圧下で成膜可能なミストCVD装置を使用したスマートウインドウ等への応用に向けた窒素ドープVO2薄膜の形成
-
加納 大成
(京都工芸繊維大学大学院電子システム工学専攻 半導体工学研究室) - 痛みのない経皮薬物投与のための小形超音波トランスデューサの開発
-
山本 真也
(東京工業大学工学院機械系機械コース 進士研究室) - 生体外での腎オルガノイドへの血管新生
-
塩田 拓輝
(東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻 酒井西川研究室) - 透明ガラス形状を維持する潜熱蓄熱材料の創製
- 菊地 真魚
(山形大学大学院理工学研究科 松井淳研究室)
テーマ概要(クリック)
テーマ概要(クリック)
テーマ概要(クリック)
テーマ概要(クリック)
テーマ概要(クリック)
テーマ概要(クリック)
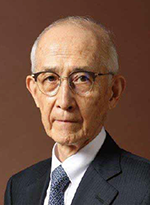
神永 晉
東レ株式会社 社外取締役
コメントを開く(クリック)
応募された51件の論文はいずれも甲乙つけがたい立派なもので深く感銘を受けました。どの論文も研究のポイントを的確に理解してほしいという熱意が伝わって来るハイレベルなものと言えます。中でも、工学の範囲にとどまらず、異なる分野へのアプローチとその融合を研究目的としたものが少なからず見られたことは注目に値します。
研究は自分の専門を究極まで深めることが重要であることはもちろんですが、それを基盤として他の分野への広がりを模索し、人々の幸せのためのより良い社会の構築に寄与することが、工学の研究にとって重要です。何事も単に受け身で自己完結するのでなく、他者へ働きかけるものでなくてはなりません。その観点から将来への繋がりを予見させる論文が多く見られたことは大きな楽しみです。今回の選考結果にかかわらず、皆さんの研究が将来に向けて更に深化することを期待します。

竹内 佐和子
東京音楽大学 特任教授、東レエンジニアリング株式会社 技術顧問
コメントを開く(クリック)
今回の評価ポイントは、身近な生活環境から思いついた開発テーマを先端技術に結びつけ、将来の市場化まで見通すプロセスです。全国から届いた応募は、宇宙工学、通信、医療、情報技術にわたり、研究姿勢は甲乙つけがたく、意気込みに拍手喝采です。次の課題は新技術を産業界にどう移転するかになるでしょう。それにはターゲットとなる産業や地域に接点を作り、早い段階で社会に投げかけ、反応を取り込み、開発プロセスを加速する必要があります。独自のコンセプト作りも必要です。
「社会的インパクト」は急速な高齢化、構造物の老朽化、投資意欲の減退という「ねじれた」現実にテクノロジーでどう立ち向かうか、を問うています。多くの人々は技術の新旧に関係なく豊かで人間的な生活を願います。そういう世界にアピールする技術やルートを開拓するため、今後は国際的に、かつ点から面に広げて取り組んでほしいと思います。

黒田 秀樹
CMディレクター、信州大学 特任教授
コメントを開く(クリック)
手塚治虫氏の描く未来図を読み解くようでした。工学的見地による問題意識を基に、プラズマ電界、血管新生などミクロなテーマから、空間経済モデル、宇宙への探究などマクロなテーマまで多岐にわたることに驚きました。自分にはおのおのの研究を正確に理解する知見はありませんので、表現力や社会的インパクトをポイントに審査させていただきました。結果、普段使わない脳の回路がチクチク刺激を受け、圧倒された次第です。
一方、独自の研究のプレゼンには分かりやすさこそ必要です。図解を含む表記が自己完結しているものも多くありました。伝達力を磨いてさらなる対外的飛躍を期待します。現状の環境や事業に対する疑問や怒りをモチベーションにした研究者には、青色LEDの中村修二氏を重ねました。山中伸弥氏、本庶佑氏、真鍋淑郎氏に続く研究者は確かに存在します。誇らしく頼もしい学生たちを応援します。
2023年12月12日付け日刊工業新聞4面「第1回 修士研究応援 TRENG Support」 ダウンロード
併せて2023年10月16日付[プレスリリース]工学系大学院での研究を応援する取り組み「TRENG Support」の当選者を決定もご覧ください。